『桃太郎@紫』 by みかん 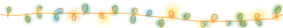 注)R18表現あり 毎度のエロギャグです。 速水さんが3枚目気味ですし、マヤちゃんもおかしいです。 許せる方のみどうぞ…。 ≪市○悦子のナレータの声でお読みください≫ 昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。 姓は速水で、名はそれぞれ真澄とマヤでした。 おじいさんはおばあさんから、何故か名字の「速水さん」と呼ばれており、 家庭内離婚では、と思わせるものがありましたが、これがまた後期高齢者とは思えないほどの目も当てられないラブラブぶりでした。 おじいさんはロマンスグレーの資産家イケメンで、よく近所のおばあさん連中から恋文やら恋の俳句やらを貰っていました。 おばあさんは今も現役の女優で、現在は「紅天女〜介護編〜」の上演中であり、要介護認定1となった一真を変わらぬ愛で支え続ける、という阿古夜の姿に 全米の老人が泣き、ロングランとなっていました。 更に言うとおじいさんは、国民年金と貯蓄以外にも、 60歳までに積み立てておいた個人年金や、 土地やマンションなどの不動産収入や、 国の信用力があり格付けも高いが利息の低いオーストラリアなどの米貨に加え新興国であり政情が不安定だが利息の高い中東・アフリカ通貨などの国債をそれぞれ適度に購入し、その結果リスクが分散され安定した分配金を得たり、 あるいは海外で犯罪すれすれの行為によって得られた収益金をマネーロンダリング(資金洗浄)して自身に危険が及ばないようにしてから海外の口座に貯蓄したりと、得意の頭脳プレーによっておいしい老後収入を得ていました。 おばあさんは、良く分からないけどとりあえず毎月口座にお金が入ってくる ことに安心していました。 そんな仲良し夫婦でしたが、唯一子宝には恵まれませんでした。 ある日、おじいさん(以下速水さん)は自身の所有する山の整備、つまり 芝刈りに出かけました。 おばあさん(以下マヤ)は川へ発声練習をしに行きました。 すると、川の上流から大きな紫色の桃がどんぶらこ、どんぶらこと流れてくるではありませんか。 「アメンボあか…いえ、紫だわ!何あの桃、腐ってるのかしら…」 マヤはその桃を手に取り、触って触感を確かめたり匂いを嗅いだりしましたが腐っている様子はなく、とりあえず自宅に持って帰りました。 速水さんは、マヤの持ち帰った紫の桃を眺めながらこう言いました。 「そうか…この展開は『桃太郎』だな。マヤ、これは子宝に恵まれなかった俺たちへの授かりものだ。さあ、さっそく桃を割って桃太郎を手に入れよう。」 「ええっ!?これがあの…。嬉しい、ついに赤ん坊が授かるのね。」 マヤはナタで桃を切りましたが、中には何も入っておりませんでした。 「あれ…何も無い…でも、この桃、美味しそう…。食べてもいいのかしら…。」 おかしいな、今回のテーマは桃太郎であるはずなのに、といぶかしんだ速水さんでしたが、ハッと閃いたことがありました。 「マヤ…分かった…。よし、この桃を食べよう。」 「え…食べていいんですか?わ、分かりました、いただきます!」 その怪しい紫の外見とは裏腹に、果肉はとても瑞々しく果汁を滴らせています。 速水さんとマヤはとても美味しくいただきました。 するとどうでしょう、老人だったはずの二人の外見が、みるみるうちに若返ってきたのです。 「ええっ速水さんが!結婚したころみたいになっちゃったー!」 「マヤも…結婚したての頃の様に若々しいよ…。20代前半のピチピチお肌だ…。」 「これって…どういうことですか?」 「つまり…これは、現代で一般に知れ渡っている桃太郎のストーリーとは違う、本来の桃太郎の筋書きに沿っているのだ。」 「本来って?」 「ああ。本当は、桃太郎は桃から産まれたのではなく、桃を食べて若返った おじいさんとおばあさんから産まれた、という物語だったのだ。 しかし、明治の教育改革の際、桃太郎の話を教科書に載せるに当たって、 この部分は教育上相応しくないとのことにより、現代の様な展開に変えられてしまったのだ。」 「ええっ?そうなんですか!知らなかった…。でも、別にわざわざ昔の話にしないで、今のお話通りにすればいいのに〜。」 「マヤ…。よく聞くんだ。昔話が、子供に読み聞かせるストーリーとして相応しくないという理由で、話を一部変更したというのは良くある話だ。 だが、果たしてそれが正しいことなのだろうか?例えば『シンデレラ』では、 本当は意地悪な姉達はガラスの靴を履くためにつま先や踵を切り落として しまうんだ。」 「きゃあっ!痛そう〜」 「だが、残酷な場面や人間の欲望を、子供たちからいつまでも隠匿し続けていいのだろうか?いずれ彼らも、逃げられない現実を目の当たりにする時が来るだろう…。」 「た、確かに…。」 「その為に、事実を脚色せず次の世代に伝えていくのも、大人達の使命ではないだろうか。『桃太郎』に本来含まれていた、老人の回春願望もその一つだ…。 いくつになっても、人は若さや性への欲求があり、老人といえどもそれは例外ではないということを…。」 「そうですね…さすが速水さん…」 「さあ、マヤ…。ここで俺達はこの物語に込められた教訓を体現するんだ…それが俺達の大切な使命なんだ」 「は、はい…でも、久しぶり過ぎて何だか恥ずかしいです…」 「何を言っているんだ、マヤ…。それに、俺達は子供が欲しかったじゃないか…。さあ、仕込みを開始しようか」 「こ、子供!!そうでした…。はい、仕込んでください…速水さん…。」 速水さんはマヤの唇にそっと自分の唇を重ねました。それは、瑞々しく弾力があり、まさしく取れたての桃そのものでした。 「20年ぶり…恥ずかしい…」 「ああ、何て柔らかい唇なんだ…。まるでさっきの桃の果肉の様だ…」 彼はマヤの口内を舌でまさぐりました。マヤは久しぶりの、口の中がムズムズするような感覚に夢中になり、速水さんの首にしがみつきながら彼の舌の動きを必死で受け止めました。 速水さんは、マヤの着物の帯をほどきました。すると、まさしく20代そのものの張りを持った乙女の乳房が現れました。マヤは恥ずかしさで堪らず、両手で顔を覆いました。 「素敵だ…まるで、取れたての白桃を思わせる…」 「やん…」 体を抱きしめたまま徐々に体を傾け、速水さんがマヤの体をお布団に横たえました。マヤは恥ずかしさで目をギュッと瞑り、体を小刻みに震わせ、顔を横に向けています。そんな妻を見て、速水さんは愛おしさが込み上げてくるのを止められませんでした。 速水さんはおもむろに、その熟れた白桃を両手で鷲掴みにしました。 そして、その先端で震えている赤い果実を口に含みました。 「あっ!」 柔らかだったその果実は、あっという間に硬さを持ちました。 「んーー!!ン……ッ」 胸の先がじんじん痺れ、脳天まで届きます。 マヤは、20年振りにこんなあられもない声を聞かれるのが恥ずかしくて、一生懸命声を抑えました。 彼は、唇で挟み、乳輪の周囲を舌でなぞり、そして舌先で突き、吸い上げ、 歯で甘噛みをしました。 「……っ!!ふっ…ン…っ……」 声を殺している代わりに、彼女は速水さんの髪を執拗にひっぱり、 頭を左右に振っていやいやをし、胸を襲う甘い刺激に耐えていました。 彼の片方の指が、マヤの胸の先を転がしたり押しつぶしたり引っ掻いたりし始めました。 「あ、あァッ!いっ、あ、ヤ、ン!」 あまりに彼がじっくりと胸の先をいたぶるので、マヤはあっけなく声を出してしまいました。一度声が出るともう抑えられません。彼の唇や指先や舌の動きに合わせて、まるで短い悲鳴のような嬌声を上げ続けました。 彼女の二つの白桃を思う存分いたぶった後、速水さんはマヤの両膝を立てて 開きました。いわゆる観音開きです。(後世では、M字開脚とも言われます。) 「は、恥ずかしい…」 「恥ずかしがることは無いじゃないか、俺達は長年連れ添った夫婦だぞ…」 「で、でも20年振りだから…」 「綺麗だよ…。まるで、新鮮な桃に切れ目を入れた様だ…。」 そのまま彼は動かず、じっとマヤのそこを見つめ続けました。外の冷たい空気に晒され、又彼の視線を痛いほどに感じ、彼女の敏感な芽は尖ってゆきます。 彼の舐めまわすような視線に、マヤはますますそこが熱を持ってじんじんするのを感じました。 その時、彼が両膝に置いた手をくるりと撫でまわしました。 「……んっ!!」 その動作だけで下肢に甘い電流が走り、マヤは小さく身を捩らせました。同時に、透明な雫がその部分から溢れるのも感じました。 「ん?どうしたマヤ、俺はまだ何もしてないぞ?」 マヤは明らかにじらされているもどかしさに悶えつつ、そういえばこの人は こういうねちっこいセックスをする人だったと20年前の記憶を辿りました。 「マヤ、もうこんなに蜜が零れて…とろとろだ…」 いくら今回のキーワードが桃だからと言って、それに例えてばかりで おっさん臭い、とも思いつつ、いや中身は老人なのだからおっさん臭いということはつまり言うことが若くなったということかしら、とも悩みました。 とにかくもう早く触って欲しくて堪らなくなり、マヤは腰をもじもじと揺らし始めました。 ようやく速水さんは、マヤの可愛らしいお豆にそっと舌で触れました。 「あァ――っ!!」 期待以上の甘い衝撃に、マヤは甲高い鳴き声を上げました。 彼がそこを舌で転がす度に、ジンジンするような快感が走ります。 「あ、アん、ん、ッ」 とうとう彼がそこに長い中指を差し入れました。その途端、マヤの体の中心を電流の様な快楽が走り、たまらず背中を仰け反らせました。 しかし、20年振りのせいでしょうか、かなりの圧迫感を感じます。 まさかいきなり指を二本入れたのでは?と思ったマヤは彼に尋ねました。 「あの…もしかして、いきなり指を二本も入れたんですか?」 「いや、一本だが。なぜ?」 「え、何か、そんな感じがして…あの〜ホントですか?」 「本当だぞ。ほら、一、二、三、四」 そう言って彼は、挿入した中指以外の指で、数を数えながら順番にその周囲を叩きました。 「きゃあああああ〜〜〜!!!何て事をするんですか!!」 マヤは真っ赤になって抗議しました。 「君が尋ねてきたから証明してやったんだぞ」 「ううう…そう言われると…」 そして、マヤは彼の大切な部分に目をやると、ハッと驚かされました。 それは、新婚初夜のあの時そのままに、支えなくても天を貫いておりました。 「ああ…は、速水さん…スゴい…」 マヤは頬を染めてうっとり見とれてしまいました。 速水さんは、男らしい、自信に満ちた眼差しでこう言いました。 「マヤ…20年振りにこうなれたのも、君が桃を拾って来てくれたおかげだ… 愛しているよ…」 「は、速水さん、あたしも愛しています!」 「いくよ…マヤ………クッ」 「!!ア――――……」 彼がゆっくり入ってくると、その目もくらむような快感に、マヤは心も体も震えました。 もはや死ぬまでひとつになることはないと思っていたのに、再び二人は結ばれたのです。 「あっアッ!あ、ん、」 彼の律動が始まると、胎内の擦れる感じでたまらずマヤは涙ぐみ、思わず彼の肩に爪を立ててしまいました。 「ああ、マヤ…すごく柔らかい………果肉そのままだ…」 マヤは、まだ言うのか、とほんのちょっぴり思いましたが、しかしそんな思いは次から次に襲ってくる快感の波にどんぶらこと飲まれてしまいました。 いよいよクライマックスに差し掛かりました。 マヤは堪らず 「ああ――――!天国に行っちゃう…」 と叫び、全身から汗を噴き出しぐったりと力尽きました。 速水さんは、中身が老人なだけにヒヤヒヤするセリフだなと思いました。 そしてまた彼も20年振りに果てました。肩で息をしながら、久しぶりに味わう激しい衝撃に、腹上死しなくて良かった…と一安心しました。 こんな感じで、若返った二人は毎晩楽しくせっせと仕込みを繰り返しました。 おしまい。 後日談:その後無事赤ちゃんが産まれ、その子供は桃太郎と名づけられ鬼退治をしました。 あとがき こんなのを書いて人格を疑われそうですが、今更ですね…人生にはふざける時間も必要なのですよ…と自分をなだめてみます。 しかし、毎度ながらギャグ目線で読めばいいのかエロ目線で読めばいいのか、自分にも解らんのです…。 「明治の教育改革云々で桃太郎のあらすじが変更された」というのは 「トリビアの泉」でやってました。 「市○悦子の声」「腹上死」はももこさまのアドバイスにて追加しました。ども! 介護保険とか要介護とか、自分でもちょっと不謹慎かな、と思いました。 不愉快に思われましたら申し訳ありません。 それではお付き合いいただき本当にありがとうございました。 そしていつもながらアホですみません。 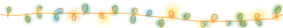 ■おしながきへ戻る |